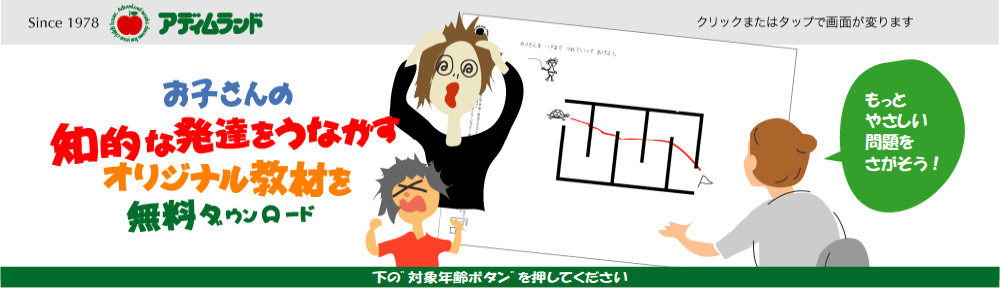人はみな同じではない
『りんご通信』2002年9月号より
こんな話があります。
ある秋の晩、お母さんが台所仕事をしていて、フト今夜はいい月夜のはずだったと気づき、縁側で遊んでいた子どもに聞きました。「〇〇ちゃん、お月さま出てるでしょ? まん丸いお月さん? それとも三日月さん?」。するとその子は夜空の満月を見上げ「まん丸いお月さんだよ。お母さん」と答えました。ところが別の子。お母さんが同じことを聞いたら、その子はフーと夜空の満月を見上げ、しばらくは月の輝きに見入っていて(きれいやなあ。あそこでウサギさんがおもちついてるってほんまやろか…どれがウサギやろ…)などと、まるで深呼吸でもするように思いをめぐらしていています。いつまでたっても返事がないので、お母さんはもう一度たずねます。「どうなの、お月さんは、まん丸い?」。するとその子は「エーとねぇ。あのね。ウサギさんがね…」。
この話は(出所が定かではないのですが)外向的な子と内向的な子の違いをイメージとして表現したものです。前者は外向的な子で、相手に返すことにスッと気持ちが向き、期待されるような答えを上手くまとめて反応しているのに対し、後者は内向的な子で、自分が内面で感じたことにより気持ちが向くため、考えがさまよったり膨らんだりしたあげく、相手には分かりにくい反応をしています。「かしこいねえ」と受け入れられやすいのは前者かもしれませんが、お月さまについてより深く感じ、考えているのは後者だという違いが汲み取れます。(ただしこの話はあくまでたとえ話なので、よくある「心理テスト」の類ではありませんから念のため)
外向的か内向的かというのは、基本的にはその人の自然な興味·関心が自分の内面に向かうか外界に向かうかの傾向の違いですが、これが子育てや教育の場に働く影響は意外とバカにできません。内向きの個性と外向きの個性とでは物事の受け止め方や反応の仕方、そして価値観までがときに正反対だったりするからです。
多くの場合、人は両方の要素をもっているのではっきりと分け難いものですが、あえて単純に言えば、外向的な人は内向的な人が分からず、内向的な人は外向的な人が分からないので、お互いに苦手でキライということになります。このギャップが親子で生じると当然ながら親子関係に影響します。ことに子どもが内向的な場合、お母さんも内向的なら子どもの心の中を分かってあげやすいのですが、お母さんが外向的だとそうはいかなくて、先の話なら「お月さんはまん丸なの? そうじゃないの? どっちかハキハキしなさいよ」などと、否定的な関係になりがちです。テンポも内向的な子はゆっくりめなのに対し外向的なお母さんは速めなことが多いので、勢い「早くしなさい!」を連発することにもなります。逆のシチュエーションでも、やはりそれ故の行き違いが生じることになります。学校や幼稚園などで、担任の先生が変わるとクラスの雰囲気や子どもの様子が変わることがありますが、これにも向性が関わっている場合が少なくありません。
価値観の違いはこんなエピソードを生みます。小学校の低学年のクラスで子どもたちが家へ持ち帰る作品づくりをしていましたが、ある子の作品はちょっと子どもの手に余りそうだったので先生が少し手を加えておいてあげました。ところがその子は、「これはもう私の作品じゃない。私が作ったものをお母さんにあげたかったのに」と泣いて悲しんだというのです。この子にとって重要なのは傍目の出来栄えといった外的な価値ではなく、自分でやり遂げることで得られる内的な価値だったのです。もしこれが外向的な子どもだったら、出来栄えの良さという外的な価値に満足し、喜んで持ち帰ったかもしれません。
こうした向性の違いはとりわけ子どもの社会的な対人態度に現れます。例えば、ふと子どものしぐさや言葉づかいがおかしかったり可愛かったりすると、大人は思わず笑ってしまうものですが、これを受けた子どもの側の反応はさまざまで、ことに座の中だったりすると、外向的な子はますますはしゃぎだすのに、内向的な子はとたんに傷ついたとばかり引っ込んでしまってウンともスンとも言わなくなるといった違いです。
向性は人の個性であって、どちらが望ましいわけでもありません。互いに異なる得手·不得手をもって補い合う性質のものです。親でも先生でも、子どもに対しては自分の向性がどうであれ、それを越えた視点で配慮を払うべきでしょう。